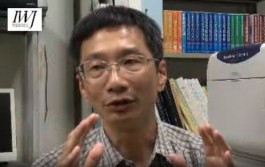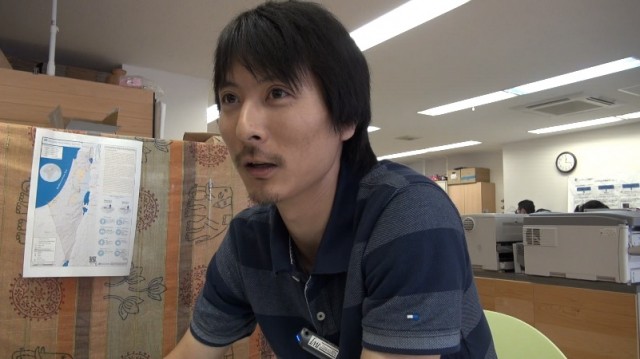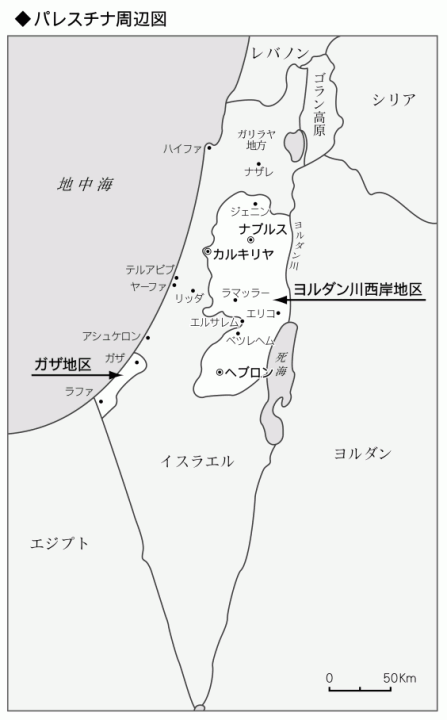特集 中東
(前編の続き)
※インタビュー前編はこちら
7月18日、3日前に帰国したばかりという、日本国際ボランティアセンター(JVC)の今野泰三さんに、パレスチナ・イスラエル問題について話を聞いた。前編では、普段のガザの暮らしや、イスラエル市民の感情についてお伝えしたが、後編では、パレスチナとイスラエルを行き来する今野さんの目線で切り取った「ハマース」や「イスラエル兵」の姿についてお届けする。また、今野さんはまさに、安倍首相が救出の対象とした、「海外の紛争地で働くNGO職員」の一人である。インタビューは当然、日本の集団的自衛権の話にまで及んだ。
- 記事目次
- ハマースとパレスチナの人々
- イスラエル兵について
- 解決策はどこに
- 情報戦
- イスラエル国内の歴史教育
-
ハマースとパレスチナの人々
Q. ハマースについて教えて下さい。彼らはどういう存在で、パレスチナの普通の市民とはどういう関係なのでしょうか
![DSC02272]()
ジャバリヤ市でJVC事業の一部として、栄養失調児の検査をするパート ナー団体アルドゥ・アル・インサーン(AEI)のスタッフ(右)とボランティアをす る地元女性(左)。2014年5月20日ー写真:今野泰三
ハマースの正式名称は、「イスラム抵抗運動」。パレスチナ人のグループです。イラクのISISやヒズボラとは全然違う組織で、パレスチナ人の民族的な権利やムスリムであるという権利を求めていく、というのが一つ根幹にあります。
ハマース憲章が常に問題になるのですが、そこには、「パレスチナの土地がイスラームのワクフ(寄進地)」であると書かれています。ハマースはオスロ合意にも反対していましたが、現実政治を見ていると、イスラエルはもう存在しているし、2国間でも仕方ない、と。強い国だからそれはそれで認めて、自分たちの民族的な自決権を認めてもらう、東エルサレムに関しては、自分たちの町であり首都であることを認めてもらう、西岸からの入植者は全部撤退する、グリーンラインを境界とする二国間でも仕方ないんじゃないかという人たちも、ハマースの中にちらほら出てきています。しかし、イスラエル軍は「ハマース」という理由だけで、そうした人々まで暗殺してきたのですが。
今、ハマースが停戦の条件として挙げているのは、難民の帰還権については全然挙げていなくて、基本的にはオスロ合意の取り決めを、イスラエル側がちゃんと守れということを言っている。その内の一つは封鎖の解除、それも一方的な解除ではなく、国連と第3ヶ国が管理、監視した元での封鎖の解除です。後は港の解除。後は海も4方向封鎖されているので、5kmくらいしか自由にいけない。5kmだと漁業が全然できないので、それをもう一回戻して欲しいということですね。
Q. オスロ合意の取り決めに戻るというのは、真当な要求に聞こえますが
民間人に向けてロケットを撃つということは戦争犯罪なので、それは認められないと思いますが、今、ハマースが要求していることの中身自体は、その大部分において、国際法に基づいた正当な要求だと思います。
ただ、ハマース=テロリストというレッテルが世界中に貼られているので、何を言っても聞いてくれないというのが現状だと思いますね。
Q. イスラエル政府は、ハマースの要求に耳を傾ける気はあるのでしょうか
実際は、水面下では常に会っているというか、全くコンタクトがないわけではないみたいですね。全くコミュニケーションを取らないと、誰もコントロールができなくなるので。ハマースもイスラエルも公式上はお互い認めてないが、微妙な関係にはあるようです。
今はエジプトが介入して、ハマースのメンバーと西岸の自治政府の役人、イスラエル政府の役人で停戦交渉をしている。お互い、国民の感情が常にあるので、気を使って慎重に物事を進めないといけないというのがあって、表には出てこない話だと思います。
その中で今、民間人がガザで殺されているので、何とか早く止めなければいけないし、止める義務がイスラエル政府にもハマースにもあると思います。
Q. ハマースのメンバーにあったことはありますか
誰がハマースか分からないんですよ。ガザの場合は、自治政府がハマースなので、ハマースが自治政府を運営しているのですが、政府の役人や警察官の中には、ハマースのメンバーや支持者もいれば、そうではない人もいます。少なくともハマースがやっている政府に雇用されている人たちです。その中でハマースのメンバーもいれば、そうじゃない人たちもいて、そうなのかなと思う人もいればそうじゃないという人たちもいる。良く分からないというのが、実際問題。
区別があまりつかない。彼らも区別されたくないと、なぜなら暗殺の対象になるので。だから本人たちも言いません。後、ハマースのシンパとメンバーと、政府に雇用されている人たちというのは、それぞれやっぱり立場が違う。微妙な違いがあるので難しいですね。
一般市民でも、ハマースを支持している人もいれば、支持してない人もいる。嫌いな人もいれば、好きな人もいる。一定ではありません。ただ、ハマースに関して指摘されていることは、これまでの20年間、貧しい人たちにイスラムの価値に基いて奉仕活動をしてきた。施設を立ち上げて、老人や孤児、貧しい家庭に色々支援をしてきたし、彼らが社会に参加する場所を提供してきた。家族的なつながりを作り上げてきたという指摘もされているので、そういう意味では社会に浸透しているのではないかと思います。
ファタハを支持している人たちや左派のPFLPとかDFLPを支持している人たちもいて、彼らは2007年以降、相当、ハマースに弾圧されてきたので、拷問にあったり、NGO団体を潰されたりしてきた。だから彼らはハマースが嫌いです。ただそれを表立って言ってしまうと、それで逮捕されて、何をされるか分からないので黙っているという状況ですね。背景は、複雑です。
Q. イスラエル国内では、ミサイル警報がなる度に市民はシェルター(防空壕)に避難していましたが、ガザにはあるのですか
ないと思います。そもそも、建設機材やコンクリートが入ってきていないので、普通の家も建てられないんですよね。家をどうやって作っているかというと、破壊された家から廃品回収して、鉄骨を伸ばしてコンクリにして、もう一度作っている。シェルターを作る余裕はほとんどないと思います。少なくとも一般家庭には。あったらこんなに死なないと思います。
イスラエル軍について
Q. イスラエル軍は、ハマースが学校や民家に武器を隠していると主張しています。どれだけ正しい情報を持っているのでしょうか
ある程度は持っていると思います。スパイ、協力者、「コラボレーター」と言いますが、パレスチナ人の弱みにつけこんで、イスラエル側に取り込むということはずっとしてきています。それは、金銭的なやりとりや、病気の息子がいて、病気の息子をイスラエル側で治療して欲しければ、協力しろといったように。具体的に電話がかかってきたとか、そういう話はよくパレスチナ人からも聞きます。
でも正確に100%得ていたら、今のようにはならない。ハマースからのロケット弾が止まらないというのは、それだけ把握できてないからとも言えます。
イスラエル兵について
イスラエルは男女、100%徴兵制です。 私が留学していた時は、兵役が終わった学生でも年に1回は予備兵として徴兵に行っていましたね。軍人は制服を着れば命令が絶対。「自分が正しいか間違っているかというのはそもそも問題にはならない。命令に従うことが大義だから」、という風に話していましたね。
もちろん、個人的な悩みはあると思いますが、外国人とシェアできるものではないと思います。トラウマ的なものもいっぱいあって、第二次レバノン戦争に行った人はすごい経験をしたと、悪夢で寝られない、友だちが殺された、殺したとかそういう話はいっぱい聞きました。
Q. 今後、どんな展開になると思いますか
地上侵攻が始まってしまったら、民間人がなお一掃巻き込まれます。ハマースって言っても、普段は普通の格好をして、家でお茶を飲んでいる普通の人たちなので、イスラエル兵にしたら全く区別が付かない。そういう中でどういう作戦で地上侵攻するのか分からない。そこにハマースが待ち受けているわけではないので、どうやって見つけだすのか。
イスラエル政府はハマースを滅ぼすと言っていますが、年々、ハマースが発射する数は増え、飛距離は伸びており、本当に滅ぼせると思っているのか、私は疑問です。
Q. 「自己防衛」といいながら、それが自己防衛に繋がっていない。どこかで自分たちの首をしめる結果を招いていると考えているのでしょうか
イスラエル軍は、ガザを占領しているのはイスラエルではなくハマースだと言ってますから、ハマースが全面的に悪い、自分たちが絶対的に正しいと思っている。だから続けるだけだ、という信念ですよね。
もちろんイスラエル社会には、長期的な安全保障につながらないと思っている人たちはいて、違う方法で話をすべきだと言っていますけど、その意見がどの程度、影響力があるのかは今はちょっと疑問です。若い人たちの中で、反アラブ感情、人種差別に近いものも根強くなっているのも現実です。そうなると、アラブ人とはどんなに交渉しても話し合いでは解決できないんだから、武力でやるしかないという考え方が強くなる。私個人は、それがイスラエルの安全保障につながるとは、全くもって思わないですけど。
▲イスラエルの首都、テルアビブで行われていたガザ空爆と占領に反対する市民と右派との衝突/A protest against Israeli attack on Gaza, Tel Aviv, 12.7.14
【関連記事】
イスラエルの平和運動は今―アダム・ケラー講演会
Q. イスラエルの世論は、軍や政府の決断にどれだけ影響力を持っていますか
影響は受けていると思います、イスラエルは民主国家ですから。今は少数の右派政党をかき集めてなんとか作った右派政権で、左よりも右の言うことを聞いておかないと、ネタニエフ首相のポジションは維持できないという現実があると思います。
解決策はどこに
Q. 今野さんが考える、1日でも長く平和が続くための理想的な手段とは何でしょうか
一つは武力は使わない。お互いに。それが理想ですが、解決策があったらとっくに解決していると思います。
Q. 今回の空爆で、イスラエルが新兵器を使っているのではないかという指摘も出ています
ガザは武器の実験場になっている部分はあると思います。兵器、あるいは戦略の実験場ですね。都市でのゲリラ戦に対する闘い方を実践する場所として使われてしまっている部分があって、イスラエルとアメリカ軍の関係もすごく強いですし、実戦経験というのは、ヨーロッパやアメリカに売れるものなのだと思います。
軍事の専門家ではないので分かりませんが、イスラエル軍は毎回違う戦略を使ってきます。毎回違う武器を使って、一番効果的な闘い方を常に探しているという印象は受けますね。今回も「KNOCK ON THE ROOF」と言って、小型のミサイルを打ち込んで、攻撃することを事前に知らせてから、大きいミサイルを打ち込むという戦略を取っています。それは前回はありませんでした。民間人をなるべく殺さずに、いかに、テロ組織を壊滅させるかという戦略として多分考えられていると思います。
イスラエルが買っている武器は全部アメリカの武器なので、それを、人が実際に住んでいる場所で使える国なんて世界のどこにもありませんが、ガザの場合はそれが平気で使えてしまう。国際社会も批判はするけど本当に止めようとはしませんし。
日本の武器輸出と集団的自衛権
Q. ガザの人たちにしてみればふざけた話ですが、日本も他人事ではなく、集団的自衛権や武器輸出の話がありますね
今回の空爆が始まってから、在テルアビブの日本大使館からは情報がなかなか入ってきませんでした。大使館の仕事は邦人を守ること、法律上も、そうなっているし、そういう意識でやっているのだとは思いますけど。電話がかかってきたときに、「ガザに行かないでください」とまず言われました。当然だと思いますが、その時ちょうど、集団的自衛権の話が出ていて、安倍首相が「紛争地で働くNGO職員の安全を守るために、集団的自衛権が必要なんだ」と話していたので、「何かあったら、自衛隊が送られるんですよね」と電話口で皮肉を言おうと思いましたが、やめました(笑)。
もしNGO職員が巻き込まれたら、日本政府は、自衛隊を派遣してイスラエル軍から私を守ってくれるのでしょうか。あるいはハマースから私を守ってくれるのでしょうか。そんなことしないでしょう。
まず、できないですね。私はイスラエルとパレスチナの例しかあげられないですが、一つは、イスラエル政府が、自衛隊がイスラエルの領土、領域に入ることを認めるわけがない。もし、認めるとしたら自分たちに都合がいいから認めるのであって、それは、イスラエル側に都合のいい軍隊としての機能です。
そして、もしそれをしてしまったら、アラブ諸国からイスラエルを支援しにきた国と思われるわけです。それで、私がガザに入ったら攻撃される可能性はあるし、ガザではなくても、そのレッテルを一度貼られてしまったら、他のアラブ諸国から、「日本の軍隊はガザに侵攻した、アラブの敵である」と見なされます。イラク、シリア、エジプトにいる日本人がいつどこにいてもそういう目で見られて、危険な目にあう可能性があります。
それで危険な目にあったらまた自衛隊を派遣するんですか?派遣したら同じことの繰り返しですよね。
安倍政権は民主主義を盾にして、民主的に選ばれた政府だから変えていいと、閣議決定をしてしまった。それを止められなかったのは非常に残念です。このまま行くと、日本の武器や技術が入った米軍の戦闘機、F35がイスラエルに供給されるという話なので、F35は間違いなくガザや西岸で使われる。レバノンやシリアでも使われることは目に見えている。日本の技術が人を殺すことに使われる、数年後に現実になる話だと思います。
それに対する危機感は日本社会には伝わりにくいと思います。「ガザでひどいことがおきている、かわいそうだ、なんとかしたい」と思っても、まさか日本の一流企業の技術が入っているなんて思ってもいないでしょうし、そういう状況をおそらく想像できないと思います。でも、それは間違いなく目の前にある現実で、それとセットで集団的自衛権の話がある。アメリカ軍と一緒に戦争に行きましょうという話。
想定しているのは中国だと思いますが、アメリカが日本の助けを必要とするのはイランやアフガニスタン、イラク。こういう地域にアメリカ軍と一緒に行ったら、完全に敵ですよね。アラブ社会やムスリム社会からしたら。
【関連記事】
安倍政権とイスラエルの「協力」が集団的自衛権の対象に!? ~ガザ空爆を続けるイスラエル、日本政府は過去に「武器輸出」の可能性を示唆
Q. そうなった場合、パレスチナの支援活動を続けるのは難しくなりますか
それは分からないですね。難しくなるかもしれないです。日本人に対する見方は変わってしまうと思いますから。今は、日本人は自分たちを傷つける人たちではないと好意的に見られています。ヨーロッパやアメリカみたいな、何を考えているか分からない政治的な理由で支援する人たちとは違って、自分たちと同じ目線で何とかしたいと思って来ていると。信用できる人たちと思われているのは、政治的な部分で目立たないからでしょうね。
Q. アラブ諸国全体でそう見られているのですか
でも、それも少しずつ変わって来ていて、イラクに派兵されたことは知られていますし、「どうせ、日本はアメリカの後ろにくっついているだけなんだろう」とたまに言われることもあります。今は「たまに」でも、それが増えていくと、日本のパスポートは安全ではなくなるんだろうなと思います。そうなった場合、安倍首相がいっている「日本人を守るために」という理由が逆転してしまいますよね。集団的自衛権を行使したからこそ、危険に晒される日本人が増える。それは国民を守ることになるのですか?その理由は筋が通っているんですか?と私は疑問に思うし、問いたいですね。
情報戦
Q. パレスチナとイスラエルの話に戻りますが、今回、パレスチナを支持する人たちが、シリアの内戦写真や合成写真などをSNS上で拡散したことが目立ち、それがBBCでも報じられました。情報戦について教えて下さい
パレスチナを支持する人たちの間で、本当に現状を世界に伝えたいという意思があるのであれば、慎重に事実確認をして伝えるべきだと思います。誤った情報は逆効果になってしまいますので。
一方、イスラエル政府の中にも宣伝省みたいな省庁があり、国の正当性を高めるための戦略が取られています。イスラエルのネット新聞、Ynetも報じていましたが、今回のイスラエルの攻撃の正しさをブログやネットで情報発信するために、400人がボランティアで集められたと。
Q. 興味深かったのが、例えばNHKの報道一つを取って、イスラエル支持者からはNHKはアラブよりの報道しかしないという声が目立ち、パレスチナ支持者からは、NHKはイスラエル寄りだという真逆の批判がありました
中東がそういう場所だから、というのは乱暴な言い方かもしれませんが、例えば、クルド人からしてみれば、イスラエル万歳なんですね。アラブ人をやっつけているイスラエル人万歳と。クルド人はそれまで、アラブ世界で抑圧されてきたので、イスラエルを熱烈に支持したりする。シリアでもシーア派、スンニ派問題があり、レバノンでもあれだけの内戦状態で、泥沼の殺し合いをしていたりする。一つの正しい意見というのは、多分、中東には存在しないのだと思います。
ただ、パレスチナ人からしてみたら、イスラエルが建国されたことで自分たちが追い出されて、難民にさせられて、さらに封鎖されてどうにもならない。人間の最低限のレベルで暮らし、人間性を否定させられるような生活を強いられているという現実の中で、彼らから見えているものは、彼らにとってはやっぱり正しい。
それをイスラエル人が受け止めるかどうかというのは、イスラエルの問題で、それを受け止めないという選択を今は取っていますけど、それがいつまで続くのでしょうか。本当に、イスラエルの安全保障にとって正しい道なのかどうかは、第三者から見ていると、このままでいいのか疑問に思います。
イスラエルの中で育っているイスラエル人は、軍隊に行き、イスラエルが常に攻撃に晒され、ユダヤ人は常に差別されているという意識がやはりすごく強い。それは、教育の中で植え付けられたものであるし、家族の歴史がそもそもホロコーストの歴史を持っていることもあります。イスラエル以外に帰るところはないだから、守らなければいけないという意識がある。それに、軍隊でやってきたことを否定すると、自分の人生を否定することにもなるので、そこは否定できない。そうした色々な事情があるとは思います。それを守るために、イスラエルの一方的な主張が正しいと、言い続ける気持ちも分からないでもありません。ただ、現実としては、世界はそのように動いてない。だから、あまり過剰になってしまうと自分たちに跳ね返ってくるのだと思います。
Q. イスラエルが孤立してしまうと?
そうなんです。ただ、孤立するということは、ある意味、イスラエルにとっては、自分たちの正しさでもあります。国を守る理由にもなるし。残念ながら答えはないというか…。よくユダヤ人がいうのは、「いくら非ユダヤ人のいうことを聞いても、結局お前たちはユダヤ人だと言われるし、聞かなくてもやっぱりユダヤ人だねと言われる。どっちにしてもそこからは逃れられない」と。
それを、第三者がどうこうするというのは、難しいです。ただ、一つ、JVCとしては、国際人権法は守られるべきだという立場です。なので、そういう意味でイスラエルが何を言おうが、ハマースが何を言おうが、やっていることが国際方に違反すれば「違反」だということ。それだけの話です。裁判をして決着をつけて、イスラエルが国家として国連で承認された国である以上、国際法は守るべき立場にあるので、一般の民衆の感情は横に置いておいて、国際法は守らなければいけない。じゃないとイスラエルの立場も悪くなりますよ、ということですよね。
Q. 国際法に違反しているイスラエルに対し、国際世論がもっと声をあげるべきだと
国際世論も声をあげないとですし、アメリカが拒否権を使うことをやめないといけない。
ただ、ヨーロッパとアメリカはもう解決策を出しています。イスラエルとパレスチナの二国間、主権を持った二つの国。西岸とガザでパレスチナ人たちの主権を認めるということは、欧米社会はすでに宣言しています。イスラエルが占領地ではない、ガザは危険だといくら主張しても、世界はそういう流れになっているわけで、後はどう実現するかという方法論やタイミングの部分で、意見が割れています。イスラエルの安全保障とどう両立するかで、意見の対立が起きているということです。
イスラエル国内の歴史教育
![DSC00926]()
◆ジャバリヤ市でJVC/AEI事業の活動(地元で入手可能な安価で新鮮な野菜・果物を使って栄養価の高い料理の作り方を教え、子どもの栄養失調を改善・予防することを目的としたクッキング・デモンストレーション)に参加した子どもたち。2013年11月21日ー写真:今野泰三
Q. 今野さんはいつパレスチナに戻るのですか。前回と全然違った街の風景が広がっているのでしょうね
8月末に戻る予定です。復興するのも早いですよ。慣れている、という言い方は悪いですけど、破壊されて直して、破壊されて直してと彼らはやってきています。破壊されると復興支援や国際援助も入ってくるので、仕事も生まれる。悲しい話ですが…。
そうでなければ、ガザがどんどん忘れられているといくと思います。ニュースにはなりませんが、空爆はこれまでも日常的に行なわれてきたし、去年度もイスラエル軍による攻撃で25人が殺されています。ある意味、空爆と封鎖が日常化しています。希望もなにもない状況の中で、大規模の空爆をうけて初めて世界の注目を浴びるという皮肉な状況があるんです。
Q. イスラエル市民が、今以上にガザの現状を知ることは必要でしょうか
ガザはイスラエル人にとっては恐怖の塊というか、怖いというイメージしかないと思います。でもいくら相手を潰そうとしても、同じことをやったら違う勢力が出てくるだけです。人を、一方的に殺してもなんとも思わない人たちはいません。それは憎しみに変わり、苦しみに変わり、それが違う形で出てくるだけで、繰り返されるだけではないでしょうか。
最近、イスラエル国内で、歴史をちゃんと教えないということが問題になってきています。何もないところに2000年をかけてようやく自分たちの土地に戻り、国を作った、そういう歴史として教えると、パレスチナ人の言っていることは理解できないと思うんですよ。
パレスチナ人にしてみれば、国ができて追い出されて今に至る。それを、ちゃんと教えないといけないと思うんですよ。実はそれを教えている学校が出始めています。左派の私立校ですが、教科書はある程度自分で作って教えられるので、イスラエル、パレスチナの歴史両方を教えましょうという取り組みも行なわれています。ユダヤ人とアラブ人の共存を目指す村を作ったりとそういう試みが少しずつ広がっていけば、他に解決策がないという中で、変わってくると思います。
共存を懐かしむパレスチナの人々
パレスチナ人も言うほど、ユダヤ人を嫌いなわけではないんです。彼らは反ユダヤ主義者ではないですし。ユダヤ人だから反抗しているわけではない。単に、自分たちを追い出して、今だに追いだそうとしてることに抵抗している。それを理解した上で話し合っていけば、何かしらの解決策はあると思っています。
パレスチナ人の原則的な立場としては、併合は違法であり、受け入れられないと言っていますけど、少なくとも東エルサレムに住むパレスチナ人の中には、「イスラエル政府の方がましだよね」という意見もあります。イスラエルが経済的にも上ですし、技術も持っているし、知識的にも上だったりするので。はっきりは口に出さないけど、併合を受け入れている人たちは少なからずいます。
ガザについても、67年から93年、オスロ合意までは、イスラエル側で働いていた人たちは何十万人といたので、今の40代〜60代の人たちは、いい思い出を持っているんですよね。イスラエル人と一緒に働いて、「ガザにイスラエル人が遊びにきて魚を食べていった」と、私にも話してきます。「ああいう時代が良かった」、「戻りたい」と。
そういう関係を作る努力をしていかなければいけなくて、その為には、まず、ガザを封鎖して、ひたすら苦痛を押し付けるような状況は終わりにしないと、問題解決には一歩も近づかない。逆に遠のくと思います。少しずつ封鎖を解除していき、パレスチナ人に生きるスペースを与える、息ができる生活の場を与えるというのは、安全保障上も、人道的にも、道義的にも絶対に必要だと思います。
Q. 以前、「プロミス」という映画でイスラエルとパレスチナの子どもたちが交流するというプロジェクトがありましたね
私も交換留学などをやればいいなと思っているんですよね。プロミスのような活動も、小さい時から長く続ければ、やはりそこは人間同士なので意味があると思います。やっぱり考えるわけじゃないですか。仲の良かった人たちが向こうにいて、そういう目にあっていたら。
※映画「プロミス」ーhttp://www.amnesty.or.jp/aff/about/archive_2009/promiss.html
Q. 一人の人間が考えること、行動することには意味があると
私はそうだと信じています。それが集まって初めて物事が変わっていくと思うので。(取材・文:ぎぎまき)
【関連記事】
・【IWJブログ】安倍政権とイスラエルの「協力」が集団的自衛権の対象に!? ~ガザ空爆を続けるイスラエル、日本政府は過去に「武器輸出」の可能性を示唆
■岩上安身によるインタビュー関連記事